ライカM10
かつてないほど“アナログ”なデジタルカメラ
スリムなボディの「ライカM10」は、「ライカM」システムの原点回帰を求める声に応えるように誕生しました。動画機能も、過剰な付加要素もなく、ただ純粋な写真を追及する一台です。CMOSセンサーとクラシックなISOダイヤルは、伝統と現代性を美しい精度で調和させています。
女性の武器
2010年代に「女性であること」はどのような意味を持つのでしょうか。2017年の女性たちの行進を機に、ニュースや政治の枠を超え、世界の女性たちの日常へ写真で目を向けてみる価値があります。続くさまざまな国やシリーズからの率直で繊細な写真には、女性たちの本当の“武器”──レジリエンス、あたたかさ、受容、粘り強さ──が写し出されています。ときに力強く、ときに静かに、ときに何気なく、ときに圧倒的な存在感をもって。そこにあるのは常にいきいきした本物の姿であり、だからこそ見逃すことができないのです。


















境界を越える
2010年代は、世界的な移民の動きが際立った時代です。政治的な変動、気候変動、経済的不安により、何百万人もの人々が移動を余儀なくされ、ニュースは難民の映像であふれるようになりました。アーティストのJRは、そのテーマをいち早く巨大なスケールで可視化し、大きなメディアの反響を生み出します。彼の作品が提示したのは、認識の新たな側面でした。写真が語るのは、到着や出自だけではありません。国境を越えて人々をつなぐ「そのあいだ」にある共通のもの──人間らしさです。

メキシコ~米国間
JRは、フェンスの向こうを見つめる巨大なスケールの子どもの絵を提示することで、国境政策というテーマ全体を凝縮して見せています。さらに彼は、国境を挟んだ場所に長いテーブルを置き、布を使ってその奥行きを視覚的に延長することによる、上から見るとひとつながりの食卓に見える共同の食事会を演出します。中心となるモチーフの「眼差し」は、ただ“見てもらう”ために空を見上げています。この2つのインスタレーションは、私たちの視点を大きく揺さぶります。壁そのものから目を離させ、それによって何が一番傷ついているのか、その問いへと意識を向かわせるのです。

ブルキナファソ
ジュリオ・リモンディは、マリの騒乱から逃れてきた人々が身を寄せるメンタオ難民キャンプを撮影しています。そこでは、人々が避難し、待ち、共に暮らし、行き先も定まらないまま次の一歩を考え続けています。ここでの移動は、逃避の一瞬ではなく、「続けざるを得ない日常」として写し出されています。

モルディブ
虚しい約束、打ち砕かれた希望。フィリップ・スパレクは、そのルポルタージュ作品『モルディブ – オールインクルーシブ』の中で、絵葉書のような光景の裏側にある現実を写し出しています。移民労働者たちは、リゾートの影で孤立しながら働き、南国の楽園にいながら、その恩恵をまったく受けていません。

ギリシャ
カイ・レッフェルバインのレスボス島での写真は、「到着」をひとつの中間状態として捉えています。疲れ切った人々、暫定的なキャンプ、浜辺に残された持ち物──。それらは、希望へ向かう長く危険な旅路の痕跡であり、その道のりがまだ終わっていないことを静かに物語っています。

イタリア
象徴的な新たな始まりとして、アリサ・マルティノワはリボルノで2人の若い女性を撮影しています。生まれた場所は遠く離れていても、2人はどこかでつながっている。出自や将来といった問いから離れたところで生まれる、帰属の一瞬です。
私たちを結び付ける、接点を見い出す瞬間が好きです。– サラ・M・リー

すれ違いざまの一瞬に
サラ・M・リーは、どんなに刹那的な出会いでも親密さが生まれることを証明しています。『優しい夜鷹』では、ロンドンの人々を、夜と朝のあいだに漂うような状態でとらえ、覗き見る視線も、つくり込まれた演出も介在しない、ありのままの憂愁と人間味を写し出します。リーは同じ鋭い感性をもって、セレブリティのポートレートからイベント撮影、静物に至るまで、幅広いジャンルを行き来します。常に一貫しているのは、被写体の本質へと私たちを近づける、澄んだ強い眼差しです。

新世代の力
The Ocean Cleanupは、河川や海洋からプラスチックごみを除去する技術を開発しており、これまでにすでに1,600万キログラム以上を回収しています。しかしダグ・メヌエズが捉えるボヤン・スラットとそのチームの姿は、荒海を行く冒険家ではありません。そこに写るのは、ノートパソコンや模型に囲まれ、気さくな会話を交わす日常の風景です。この“普通さ”は、昔ながらのヒーロー像よりも、むしろ強く人を動かす力を持っているのかもしれません。なぜなら、こうしたプロジェクトこそ、先見の明のある若い人々が画面の前から現実世界へとポジティブな変化を推し進めていることを示しているからです。そして未来を見据えるまなざしにも、確かな希望が宿ります。



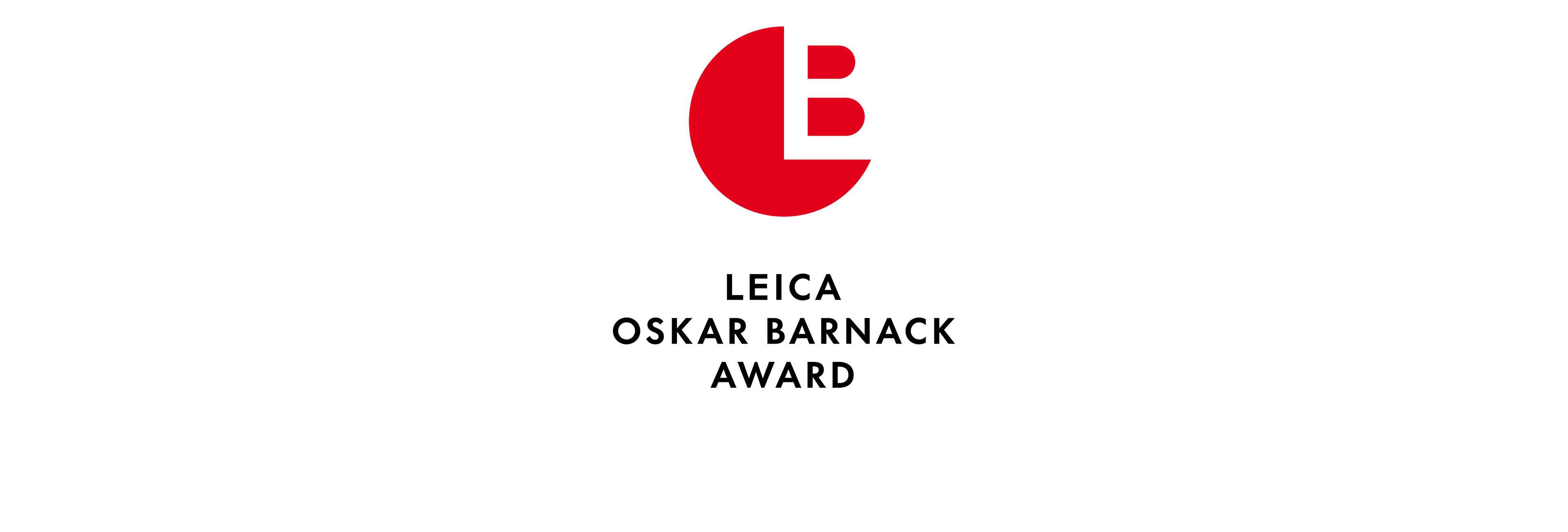
LOBA 2010–19
過渡期
自己演出とデジタルでの絶え間ない存在感が時代を特徴づけたこの10年、ライカ・オスカー・バルナックアワードは、ドキュメンタリー写真の世界的な指標としてますます重要性を高めていきました。受賞者たちが語るのは、移り変わりのただ中にある「本物の生活」です。より複雑に結びつき、傷つきやすくなった世界での共感、尊厳、そして親密さ。彼らの作品は、スピードを増し続けるイメージの流れに、静かで丁寧な観察を提示するものとなっています。

2010
イェンス・オロフ・ラストハイン
『未来を待つ』でラステインは、戦争と停滞のはざまに取り残されたアブハジアの人々を撮影しています。彼のパノラマ写真は、広がりと親密さを同時に抱え込み、未来がいかに不確かなものか、そして「待つ」という行為そのものにも、どれほど大きな尊厳が宿りうるのかを静かに示しています。

2011
ヤン・グラールプ
グラールプは『ハイチ – 震災後』で、2010年の地震後のハイチで営まれる生活を記録しています。深いモノクロームのトーンで描かれるのは、苦しみ、生き抜く力、そして連帯。痛みと尊厳が同時に存在する姿です。彼のルポルタージュは、目をそらしたくなる現実を、手で触れられそうなほど生々しく提示しています。

2012
フランク・ハラム・デイ
『Alumascapes』では、フロリダの夜の闇に浮かび上がる照明付きのキャンピングカーが、小さく完結した“理想の世界”のように見えてきます。ハラム・デイは、社会が人工的な安心感へと退避していく姿を描き出します。まばゆい表面は、そのまま外界から身を守る盾のようでもあります。彼の静かな観察は、現実が外で押し寄せ続ける一方で、逃避がどのように“もうひとつの世界”へと変わっていくのかを可視化しています。

2013
エフゲニア・アルブガエワ
作品シリーズ『ティクシ』は、アルブガエワが幼少期を過ごした北極圏へと旅をし、その原点に立ち返る中で生まれました。雪と光、果てしない地平線に囲まれた世界で、彼女はひとりの少女を追います。そこには、自らの帰属への詩的な記憶と、厳しい寒さと静寂の中で生きることへのオマージュが同時に息づいています。

2014
マーティン・コラー
『フィールドトリップ』でコラーは、イスラエルにおける「管理」と「日常」のあいだにある風景を観察しています。訓練場、待つ時間、奇妙なルーティン──彼の精密で、ほとんど映画の一場面のような写真は、常に非常事態に備えているかのようなこの国において、「普通」であることの不条理を浮かび上がらせています。

2015
JH・エングストレーム
『Tout va bien』は、は、エングストレーム自身による視覚的な自己への問いかけです。ぼやけ、身体性があり、飾り気がなく正直な写真たちは、優しさと不安、親密さと距離感のあいだを揺れ動きます。それは、彼自身のアイデンティティや記憶、そして瞬間がもつ儚さをめぐるシリーズです。

2016
スカーレット・コーテン
『宿命』でコーテンは、アラブの男性性にまつわる固定観念を打ち破ります。彼女のポートレートは、親密さと敬意に満ち、優しさや迷い、そして強さを写し出します。それは、中東におけるジェンダー観と変化についての、静かで力強いステートメントとなっています。

2017
テリエ・アブスダル
『焼畑』でアブスダルは、「森のフィンランド人」と呼ばれる人々の神話的な暮らしを語っています。霧、儀式、光のあいだに生まれるイメージは、歴史と伝承を溶け合わせ、アイデンティティと出自をめぐるメランコリックなまなざしを形づくっています。

2018
マックス・ピンカーズ
『赤いインク』でピンカーズは、あまり目にすることのない“舞台”としての北朝鮮を探求しています。演出されたイメージが支配する世界の中で、真実とは何かを問いかける試みです。彼のシリーズは精緻で奥行きがあり、権力、認識、そしてプロパガンダをめぐる視覚的な考察となっています。

2019
ムスタファ・アブドゥルアジズ
作品シリーズ『水』でアブドゥルアジズは、洪水から干ばつまで、あらゆる局面を通して“水”という要素を世界的なスケールで描き出します。それはすべてを結びつけ、同時にすべてを終わらせる力をもつ存在です。静かで荘厳なイメージを通して、彼は人間が自然に対して負う責任と、そこにある深い依存関係を語っています。